
仲田錦玉(なかたきんぎょく)
仲田錦玉 略歴
1970年 石川県小松市生2003年 二代錦玉に師事
2013年 全国伝統工芸品公募展入選
伝統九谷焼工芸展入選 以後多数入選
2016年 九谷焼伝統工芸士に認定
2017年 石川県伝統産業優秀技術者奨励賞を受賞
おおむらさきゴルフ倶楽部理事長杯の優勝杯を制作
2019年 日本伝統工芸士会作品展にて一関市長賞を受賞
2020年 全国伝統工芸品公募展入選
※販売期間11月11日(月)12時~
※こちらの作品はたち吉オリジナルではございません。
※作品の再入荷の予定はございません。
【ご使用上のご注意】
電子レンジのご使用は、おすすめいたしません。
食器洗浄乾燥機のご使用は、おすすめいたしません。
【器の個体差について】
全て手作業で行われているためサイズや形状、色味がそれぞれ多少異なります。
サイズ表記と若干の差があることをご了承ください。
個々の違いを手作りの味わい、意匠としてご理解いただきますようお願いいたします。
最近チェックした商品
アイテムで選ぶ
特集ピックアップ
たち吉オリジナルの器シリーズ

白 菊
1983年8月の発売以来のロングセラー商品。菊のリムがきりっと美しい、白い器のため料理が映えやすく、和食だけでなく料理のジャンルを問いません。

灰釉草文 はいゆうそうもん
たち吉の器のあるべき思いと、作り手の思いを同じくする器 灰釉草文シリーズ。その思いと、灰釉は、その自然な美しさが器のルーツともいわれることから、270周年を機に復刻いたしました。

市 松
古くから日本人に愛されたその古典文様を、独特の渋さを持つ緑の織部釉とやや赤みがかった白の志野釉で塗り分け、京らしい季節の絵柄をちりばめた、職人の手仕事を感じさせる一皿です。

粉引染花 こひきそめはな
陶器ならではのやさしい白さの粉引に、藍色の染花のアクセント。粉引独特の風合いがあたたかみをもたせ、くっきりとした白と染花の藍色が食卓を明るくします。

はるか
菊の花をかたどり、内外に小花柄を描いた可愛らしい器です。使い勝手がよく、華やかさを持ちながらも気取らない雰囲気です。

あかつき・玄風
ロングセラーの京焼・清水焼の湯呑とごはん茶碗。貫入釉のやわらかさとシンプルなデザインと豊富なカラーバリエーションで、ご家族みんなで色がわりで楽しむのもおすすめです。

浮 雲
シンプルさのなかにもどこか温かみが感じられるたち吉の「浮雲シリーズ」。「緋色(ひいろ)」と呼ばれる赤味が浮き出る化粧土を使用しており、その出方は一つ一つ異なるので、やきものの面白さや個性が味わえます。

粉引彫文 こひきほりもん
少したわませた楕円の形に、温かみが宿る粉引の器。ひとつひとつ施された線彫りが、器に独特の趣を与えています。「粉引」とは、「粉を引いたように白い」と表現されたことが由来。




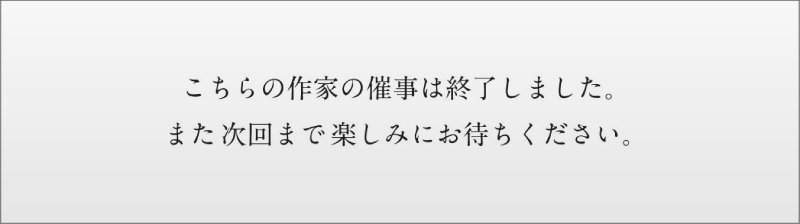





仲田錦玉 nakatakingyoku
九谷焼の代表的な技法のひとつ「盛金青粒画風」が魅せる仲田錦玉さんの作品。昭和22年に初代錦玉が錦玉窯を開窯し、庄三風画風でその礎を築き、二代錦玉が独自の盛金技法と青粒技法により、盛金青粒画風を九谷焼の代表的な画風の一つとして確立されました。令和の時代になって、白金を盛り上げて絵付けをする白金盛の技法を確立し、従来の盛金技法と合わせて絵付けすることにより、清らかで美しい雰囲気を醸し出します。作品が魅せる九谷焼の煌びやかな表情と、精巧で丁寧な手仕事をご覧ください。
青粒・白粒(あおちぶ・しろちぶ)
下地の上に一粒一粒、イッチン描きの手法で、緑絵具・白絵具を落としていく上絵の盛り上げ技法。渦や青海波などの文様を描き、大きさや感覚、下地の色を変化させて、立体感のある新たな色絵です。この技法を伝える職人が少ない今、仲田錦玉は第一人者として注目を集めています。
盛金絵付(金盛・白金盛)
文様部分をベンガラなどで盛り上げ、その上から筆で金や白金を塗る技法。漆芸の高蒔絵にも似て、立体的な表現できます。明治15年に、金沢の清水美山がはじめ、明治から大正時代の九谷焼に盛んに使用されました。二代錦玉はこの技法を吉崎東山から学び、さらに独自のものに進化させたています。