
奈良一刀彫の里を訪ねて
髙橋勇二 略歴 yuji takahashi
1952 秋田生まれ
1972 川口神泉氏に師事(’76迄)
1977 奈良県伝統工芸聴講生(’79迄)
1978 大阪市立美術研究所在籍(’82迄)
1980 関西展 入選
1981 秋田県展賞 受賞
1982 奈良県展 市町村賞 受賞
1983 天理ビエンナーレ展 入選
奈良県桜井市在住
畑村龍哉 略歴 ryuya hatamura
1999 大阪府生まれ
2018 元展美術協会 新人賞
2019 Prague Quadrennial 新人部門 選出
2021 大阪芸術大学 卒業制作展 学長賞
髙橋勇二に師事
2024 東急プラザ「藤巻百貨展」出品
Head Art Photo Contest Akashi「POLA BlueNote賞」受賞
最近チェックした商品
アイテムで選ぶ
特集ピックアップ
たち吉オリジナルの器シリーズ

白 菊
1983年8月の発売以来のロングセラー商品。菊のリムがきりっと美しい、白い器のため料理が映えやすく、和食だけでなく料理のジャンルを問いません。

灰釉草文 はいゆうそうもん
たち吉の器のあるべき思いと、作り手の思いを同じくする器 灰釉草文シリーズ。その思いと、灰釉は、その自然な美しさが器のルーツともいわれることから、270周年を機に復刻いたしました。

市 松
古くから日本人に愛されたその古典文様を、独特の渋さを持つ緑の織部釉とやや赤みがかった白の志野釉で塗り分け、京らしい季節の絵柄をちりばめた、職人の手仕事を感じさせる一皿です。

粉引染花 こひきそめはな
陶器ならではのやさしい白さの粉引に、藍色の染花のアクセント。粉引独特の風合いがあたたかみをもたせ、くっきりとした白と染花の藍色が食卓を明るくします。

はるか
菊の花をかたどり、内外に小花柄を描いた可愛らしい器です。使い勝手がよく、華やかさを持ちながらも気取らない雰囲気です。

あかつき・玄風
ロングセラーの京焼・清水焼の湯呑とごはん茶碗。貫入釉のやわらかさとシンプルなデザインと豊富なカラーバリエーションで、ご家族みんなで色がわりで楽しむのもおすすめです。

浮 雲
シンプルさのなかにもどこか温かみが感じられるたち吉の「浮雲シリーズ」。「緋色(ひいろ)」と呼ばれる赤味が浮き出る化粧土を使用しており、その出方は一つ一つ異なるので、やきものの面白さや個性が味わえます。

粉引彫文 こひきほりもん
少したわませた楕円の形に、温かみが宿る粉引の器。ひとつひとつ施された線彫りが、器に独特の趣を与えています。「粉引」とは、「粉を引いたように白い」と表現されたことが由来。





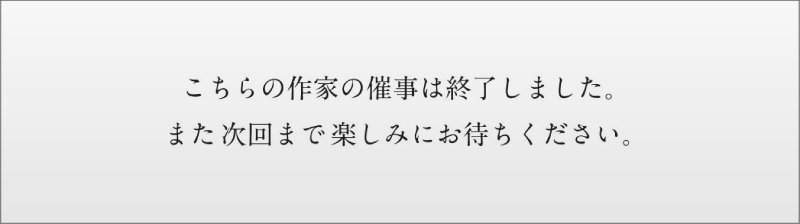





木を削る音に重なる師弟の対話奈良一刀彫
奈良県の伝統工芸「奈良一刀彫(ならいっとうぼり)」は、ノミ一本で木を豪快に削り出すことで生まれる力強さと荘厳さが魅力です。細かい彫刻刀をあまり使わず、文字通り「一刀」で力強く削り出すことで大きな面の削り跡が残り、それが力強さと躍動感を生み出しています。
この地で、奈良一刀彫を守り継ぐ職人は年々数少なくなり、髙橋さんはその貴重な担い手のひとりです。
さまざまな文化への深い理解と尽きぬ好奇心を持ち、現代カルチャーにも目を向ける髙橋さん。土地や人との出会いから得た膨大な知識は、この工房で創作へと落とし込まれていきます。
髙橋さんが「最後の弟子」と言って全幅の信頼を寄せる畑村さん。
髙橋さんのもとで、確かな技術を受け継ぎ磨きながら、若く柔軟な発想で作品づくりや新たな販路の開拓を行っています。
金箔や水干(すいひ)・岩絵の具で彩られた微細で華麗な図柄が、独特の迫力を持つ人形に見事に調和しています。
起源は江戸時代とされ、東大寺や春日大社などに奉納される祭礼具や能人形の制作から発展した奈良一刀彫。現代では、海外の観光客向けの工芸品やインテリアとしても人気があり、伝統を守りながら新しい表現も生まれています。